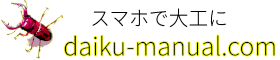鉋(かんな)の修得【プロ向け】効率的な上達方法

鉋は現代でも仕上げに不可欠な道具であり、プロの大工にとって修得すべきスキルです。
近年、鉋を使いこなせる大工は激減しています。
教える事ができる大工は減り、使用の機会も少なくなり、修得はどんどん難しくなっています。
今回は鉋の扱いを効率良く修得するための、大工に必要なスキルの概要と、最初に取り組むステップについて解説します。
目次
鉋を修得する2つの方法
1・とにかく使うこと
2・効率よく基礎となるスキルを修得する
鉋の特徴
1・精度
2・仕上げ
鉋単体のスキルについて
・用途とサイズ
・必要な3つの基本スキルについて
・用途別の必要スキル
・用途上の難易度
木の状態に対応するスキル
・仕上げにくい材
効率的な鉋の修得方法
・スキルの重要度
・おススメの練習法
大工道具(手道具)についてのまとめページはこちら
大工マニュアルのトップページはこちら
記事の作成者
 深田健太朗 京都府出身 1985年生
深田健太朗 京都府出身 1985年生
一級大工技能士や二級建築士、宅建士など住宅に関連する国家資格を5つ持つ大工です。
人生で最も高価な買い物である住宅に関わることに魅力を感じて大工職を志しました。
大工職人減少は日本在住の全ての方に関わる重大な問題だと考え大工育成のための教科書作りや無料講習を行っています。
説明用動画
このページの説明用動画です。
文字で伝えにくい部分は、映像で詳しく説明しています。
大工に必要な鉋のスキルとは
鉋は木材を仕上げる道具で、大工の他にも様々な職業で使用されています。
大工が行う木工事では様々な材料、様々な環境で仕上げを求められます。
大工は全ての状況に対応し、高い精度で仕上げるスキルが必要になります。
鉋を修得する2つの方法
1・とにかく使うこと
鉋は体で覚えるタイプの技術なので使って覚えるしかありません。
※とは言え、基礎となるスキルがないと使うことができません。
2・効率よく基礎となるスキルを修得する
鉋は、様々な技術や知識が必要になり、一部を知っても修得したことにはなりません。
加えて、鉋のように使いこなせる人が少ない道具は情報が少なく、修得の効率は悪くなります。
鉋のスキル全体を把握し、効率の良い練習方法を行うことが修得の近道になります。
鉋の特徴
現在でも、鉋でしか出来ないことがあります。
1・精度
鉋は世界で最も切れ味が必要とされる道具の一つと言われ、とても精度のレベルが高い道具です。
鉋には鉋屑の薄さを競う文化があり、削ろう会という大会が全国で行われています。
削ろう会で競われる鉋屑の厚さは、3ミクロン(300枚で1㎜)という途方もない薄さです。
2・仕上げ
鉋仕上げは鉋でしかでません。
サンドペーパーで削り上げればツルツルにはなりますが、鉋仕上げとは仕上がりが異なります。
※サンドペーパー仕上げはとても時間がかかります。
鉋単体のスキルについて
・用途とサイズ
台鉋には大きく分けて、仕上げ鉋・中仕上げ鉋・荒鉋という3つの用途があります。
それぞれの用途の目的
・仕上げ鉋
木材を綺麗に仕上げる用途で使用します。
・中仕上げ鉋
仕上げるための下地(材料の形を調整する)を作る用途で使用します。
・荒鉋
削って減らす用途の鉋ですが、現在では電気がんな(ベビーガンナ)で代用しています。
用途とサイズの関係
台鉋にはいろいろなサイズがあります。
鉋のサイズは刃口の大きさ(仕上げられるサイズ)で表されます。
鉋は必要に応じたサイズを選び、用途に合わせて調整します。
※購入時のサイズや使用によって用途が決まっているわけではありません。
・必要な3つの基本スキルについて
鉋には、切れ味・逆目止め・平面加工の3つの基本スキルがあります。
切れ味(刃)
切れ味は鉋の刃を調整します。
切れるように研ぎ上げることはもちろん、刃の形も正確に調整する必要があります。
逆目止め(裏金)
仕上げる材料の木目に逆らって仕上げた場合に、刃が食い込む力がかかり逆目が起きます。
逆目を止めるために裏金(裏刃)があります。
※裏金を使用せず逆目を止める一枚刃の鉋もあります 。
平面加工(台・引き方)
鉋は平面に加工する道具でもあり、平面加工のための定規の役割を果たすのが鉋の台です。
刃の出入りの調整よりも、平面が加工できる台を調整する知識が必要です。
鉋が調整できている状態で、仕上げの調子は引き方を調整して行います。
とても重要なスキルですので、鉋が調整できるようになったら練習が必要です。
・用途別の必要スキル
仕上げ鉋
仕上げることに必要な刃の切れ味や刃の形の調整が必要です。
逆目止めも必要ですが、仕上げ鉋は薄く削るので比較的簡単に止めることができます。
仕上げ鉋の台は平面用に調整すると材の凹み部分が仕上げられないので、多少波打った材でも仕上げられる状態に調整します。
中仕上げ鉋
中仕上げ鉋は仕上げるために逆目を止めながら材の形を調整します。
仕上げ鉋より厚く削るので切れ味も必要で、逆目を止めるのも難しくなります。
また、仕上げ鉋と刃の形を完全に一致させる必要があります。
平面を削り出すための台調整の精度も必要になります。
荒鉋
荒鉋は仕上げや中仕上げのスキルがあれば使えます。
・用途上の難易度
用途別で見ると、調整が一番難しいのは中仕上げ鉋です。
しかし、現在は機械で加工することが多く、特別な状況でない限り使用しません。
木の状態に対応するスキル
大工は様々な状況での仕上げが必要になり、大工が扱う材料は仕上げやすいものばかりではありません。
一般的に高級な材ほど仕上げやすく、安い材ほど仕上げにくくなります。
・仕上げにくい材
硬い・柔らかい・木目が巻いている・節有り・大きい・小さい・木口など
樹種による硬さの違いや、部分的な特徴、鉋のサイズによる制限などにより非常に仕上げにくい場合があります。
※木の状態に対応出来るようになるには、実際に仕上げて覚えることでしか修得できません
効率的な鉋の修得方法
・スキルの重要度
刃を調整するのスキル
仕上げ・中仕上げ共に切れ味は確実に必要になります。
刃の形は鉋を2つ以上使用する場合には特に必要になります。
裏金や台を調整するスキル
裏金の調整は頻繁に行うものではないので、人に調整してもらって、とりあえず使うこともできます。
台の調整は体で覚えるスキルではありません。
削ること自体が難しいわけではなく、勉強すれば調整することができます。
最初に修得を目指すべきスキル
一番最初に練習するべきは、仕上げ鉋の刃の調整です。
鉋の修得において、研ぎ上げや刃の形を調整出来るようになる事が不可欠であり、全ての状況に対応する基礎となるスキルになります。
中仕上げ鉋の調整は仕上げが扱えるようになった段階で、必要となれば取り組んでみるといいと思います。
・おススメの練習法
鉋の基礎となるスキルを手に入れるために、僕も行っていた効率的な方法をご紹介します。
削ろう会に出る
おススメは、削ろう会への出場です。
削ろう会には、鉋に自信のある大工さんが多数出場します。
身近にいる大工さんとは桁違いのレベルの方もいるかもしれません。
※自分の親方のレベルも、他の大工さんと比較すると凄さを実感することもあるかもしれません。
削ろう会の特徴
削ろう会で仕上げる材料(ヒバ)はとても削りやすい材料です。
大会中出場者は、ほとんどの時間が鉋の調整を行って過ごしてますので、しゃべりかけるチャンスはいくらでもあります。
知りたいことは、どんどん質問して教えてもらいましょう。
最後に
鉋は使って体で覚えるしかありませんが、いきなり使えるものでもありません。
鉋の修得が難しい現代において、削ろう会への出場は、鉋の基礎となるスキルの修得にはとても効率的だと思います。
使えるようになれば、日々の大工工事の中で節だらけの材料や、硬い材料などを仕上げていくうちに、だんだんと自信がついて修得できていくことと思います。
皆さんも鉋を修得して、一緒に大工技術を伝承していきましょう。